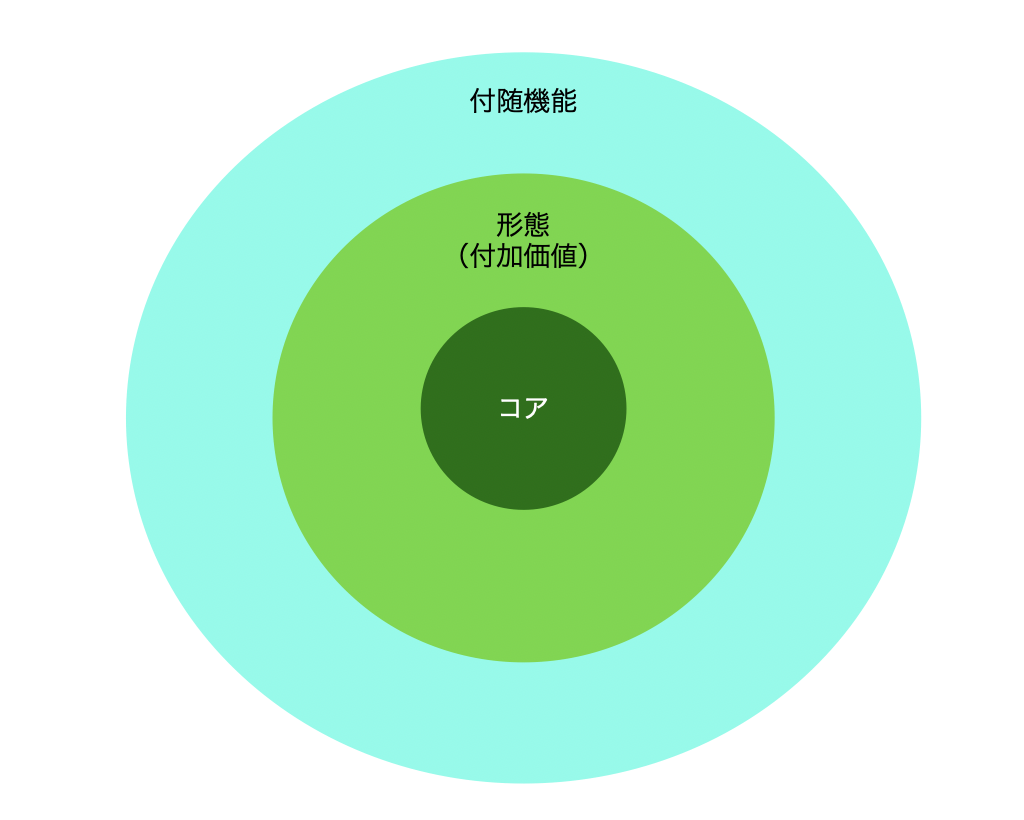昨今のコロナウィルスによるテレワーク推進の動きを受け、電子署名に関する議論が活発化しています。先般は、法務省から捺印に関するQ&Aが出されるに至りました。
電子署名の普及が以前と比べて進みつつあるのは事実ですが、こと日本においては、まだまだハードルがある、というのが私の感覚です。
ハンコの不便さやテレワークの弊害云々以前に、これまで日本企業が培ってきた文化が、ジョブディスクリプションや権限委譲を苦手としていて、それが電子署名を含む「サイン文化」に馴染まないと感じます。
ハンコ実務とサイン実務の決定的な違い
日本のハンコ実務において、名義人自らハンコを押しているケースは、ほとんどありません。何らかの会議体で決済をとり、稟議書等をもって、ハンコ管理部署がハンコを押すケースが大半です。
そこには、徹底した「責任の所在の不透明化」があります。単独の存在としてのサイナーは、ジャッジもしなければ、クロージングもしません。
一方、欧米のサイン実務においては、サイナーは自らサインをします。
そこには、前提としてジョブディスクリプションと責任範囲の明確化があります。サイナーは、自らが責任を負える(負っていい)契約であるから、自らの手で契約にサインをします。組織はそのように作られ、責任範囲があらかじめ明確化され、権限委譲がなされ、組織においてサイナー名義も細分化されます。
この「責任範囲の明確化と権限の細分化」が、「自ら書面にサインをする」というサイン文化を形作っていると感じます。
電子署名の使用で直面したこと
私自身の経験ですが、こちら側がクラウド型電子署名を使用して契約相手型に手続きを依頼した際、「決済や手続きの事情があるので、サイン名義は代表者にしつつ、手続き自体は事務担当が行いたい」という申し入れを受けたことがあります。
日本企業が、ジョブディスクリプションと権限委譲を本質的に苦手としていることを強く感じる例です。
改めて考えると、「自分のサインをするのに決済が必要」っていうの、本来おかしいですよね。
まとめ
電子署名は、ハンコと異なり、「誰が手続きしたか」が明確になります。これはハンコ実務の持つ「責任の所在の不透明化」を享受してきた日本企業には、基本的に馴染まないものです。
電子署名を本当に普及させるには、日本企業が本当の意味でジョブディスクリプションと権限委譲を欧米並みに使いこなせるようになる必要がありそうに感じます。
とはいえ、「ハンコを押すために出社する」のがバカげているのは間違い無いので、早く電子署名が欧米並みのスタンダードになってほしいな、と思います。